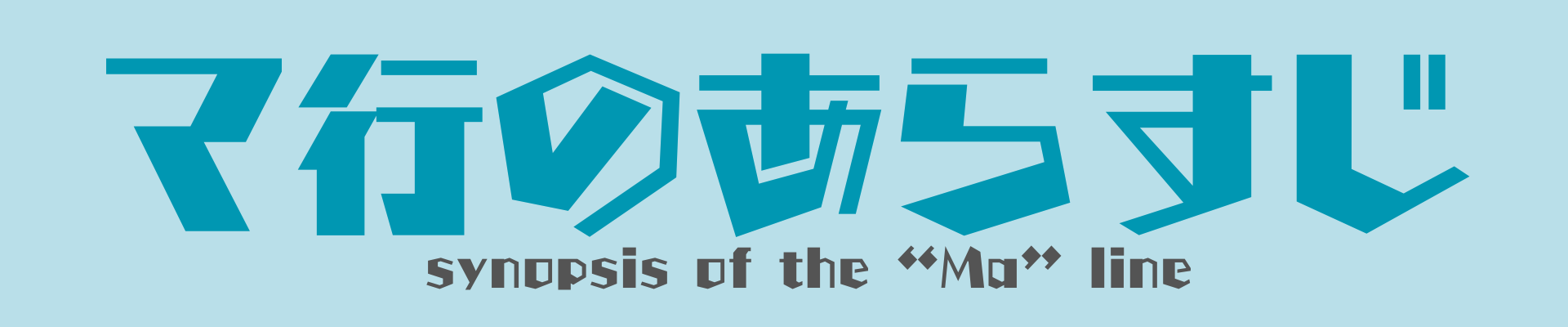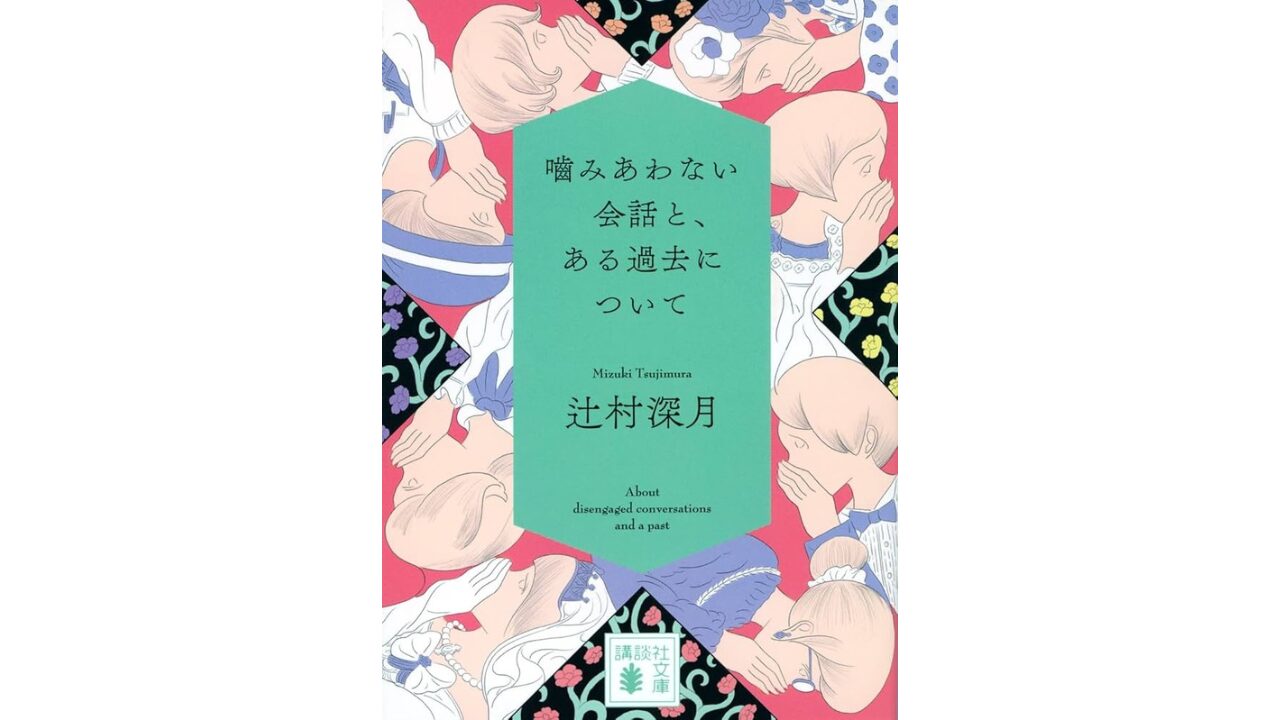噛み合わない会話と、ある過去についてのあらすじ
ナベちゃんのよめ
ナベちゃんの婚約者がヤバいらしい。
ナベちゃんは、大学時代に所属していたコーラス部の同期で、華奢な見た目と女性的な感性から、男子学生だけど女子部員と一緒にいることの多かった人。
残念ながらナベちゃんは女友達みたいな扱いで、いい人だけどモテていた訳ではない。
そんなナベちゃんが結婚する。コーラス部の同期たちはナベちゃんから、結婚式の招待の連絡とともに、事前に婚約者を紹介をしたいと言われる。
だが、婚約者がかなり気にする人なので、女子たちは直接ナベちゃんに連絡を取ることは控えて欲しいとお願いされる。
あのナベちゃんが?何様のつもり?疑問を抱えながら、ナベちゃんとその婚約者に会う日を迎える。
パッとしない子
今をときめく国民的アイドル、高輪佑くん。たすくんスマイルという輝きある笑顔や、プロ並みの絵を評価される彼の学生時代を知るのは、小学校教諭の美穂。
美穂は佑の3歳下の弟の担任をしており、佑には図工の授業を教えていた。
色んな人から佑は昔から輝いていたか聞かれるのだが、美穂の記憶ではあまりパッとせず、おとなしく地味な性格。
そんな佑がテレビの密着取材で母校に訪れることとなり、かつて佑を教えていた時の美穂と同じくらいの年齢に成長した佑と再会を果たすことに。
自分のことなど覚えているか不安になっていた美穂だが、取材を終えた佑が美穂を見つけると、声をかけてくれた。
そして、先生と話したかったとたすくんスマイルで微笑みかけられる。
ママ・はは
スミちゃんの引っ越しの手伝いをしながら、保護者会で起きた出来事を話す。
お互い小学校の教師をしており、スミちゃんは教師ならではの細かいニュアンスの悩みにも共感してくれる。
教師に刃向かう親のことを世間的にはモンスターペアレントと呼ぶが、真面目で我が子に厳しく教育しているからこそ、裏表なく真剣に問題解決したいという親もいる。
スミちゃんはその我儘でも悪意もない、ずれている親の存在にも理解を示しつつ、そういう親はきっとそのうちいなくなる、と言う。
スミちゃんはそれから子育ての正解や、親と子の対等な関係性について持論を述べはじめる。そして、不思議な話を聞いて欲しい、と言い出す。
引っ越し作業中に出てきたアルバムの中から、明るくきれいな藤色の振袖を着たスミちゃんの写真を取り出し、実はこの着物着ていないんだよね、と言うのだ。
早穂とゆかり
最近よくテレビや雑誌に出ている塾経営のカリスママダム、日比野ゆかり。子どもの個性を尊重し苦手をなくす教育方針は高く注目を浴びている。
艶ある肌に清楚な服装、微笑む顔に堂々とした貫禄を感じ、女優のようなオーラさえ感じる媒体の中のゆかりを見て、昔はこんなんじゃなかったと口に出す早穂。
早穂とゆかりは小学校の同級生で、早穂は国立大附属の中高一貫校を受験したため、それっきり会ってはいない。
教育問題を涼しい顔で語るゆかりをを見るたび、違和感を拭えない早穂。
ゆかりは地味で暗く人気もない、クラスの余りものだった。そして注目を浴びたい一心に、霊感があると嘘をついていた。
そんな過去を隠していることをより滑稽に思い、どうでもいいと無関心さが勝つ。
地元の県内情報誌のライターをしている早穂は、ゆかりの特集コーナーを担当することとなり、かつての思い出を振り返りながら会いにいく。
噛み合わない会話と、ある過去についての名言
「人生は長いからさ。大人になってから子どもに自分がやってきたことを肯定してもらえないと、いざ対等な状態になった子どもに見捨てられることになるよ。感謝されないし、仲良くしてもらえない。保護者と被保護者はいずれ、介護だなんだで逆転するんだしさ」
「周囲から嫌われ者のレッテルを貼られてしまうと、本当は自分にどれだけ自信があっても、やっぱり自信というものはすり減ってなくなるのよ。クラスの中心人物になるような子こそが正しくて、彼女たちのグループにうまく入れない自分はおかしいんだって思うようになる。あなたに気に入ってもらえるには、どうしたらいいんだろうって、そのことで私は毎日、悩んでた。仲良く、してほしかった」
「あれだって、当事者たちは、自分たちの身近にある問題ひとつひとつを『いじめ』だなんてとらえていないと思います。事例それぞれに事情が違い、メディアで紹介されているものとはここが違う、あそこが違うから、自分たちのこれは『いじめ』ではない、と思っているはずで、その意味では、メディアが言葉を作ってしまったことの罪深さを感じます。これは、『いじめ』をしている側はもちろんのこと、『いじめ』をされている側にとってもそうですね」
噛み合わない会話と、ある過去についての感想
この小説は、やった方は覚えていなくても、やられた方は覚えている。これを気持ちいいほどに落とし込んだ作品である。
私はどちらかというと「やられた方は覚えている」を強く感じる人種のため、自覚のない悪が追い込まれていく様に、いいぞいいぞもっとやれ!と、タチの悪い感情が溢れ出てきた。
傷つけようと発した言葉と、悪意なく自然に溢れた言葉。どちらが受け手にとって辛さを感じるのだろう。
そんな意味で言っていない。発言した本人がいくらそう言おうとも、受け取った側が正解になってしまう矛盾。でもそれが正義で。
言葉の奥にある含みにまで感受してしまうと、逆に受け手が過敏すぎるとも揶揄される。傷ついた結果はどうあがいたって変わらないのに。
この物語において、傷つける側に立った人たちへの救いの言葉はない。何なら認めたくない、何で自分が?なんて抗ってきたりもする。
所詮そんなものなのだろう。自分を上手に可愛がられる悪ほどめんどくさいものはないのだ。
傷つけてくる人間とは、もう一切の関わりを断つのがいちばんシンプルで効率的。見返してやりたい、いつか反逆してやるんだ、その復讐心を持っている間、無自覚にずっと傷つけられている。その人のことを思い出すたびに、気持ちがすり減っていく。
ある過去を重ねて、作品の中で発散する。そんな読み方をして、ある過去を記憶から抹消していく。本の力を借りてみるのも、悪くはない。