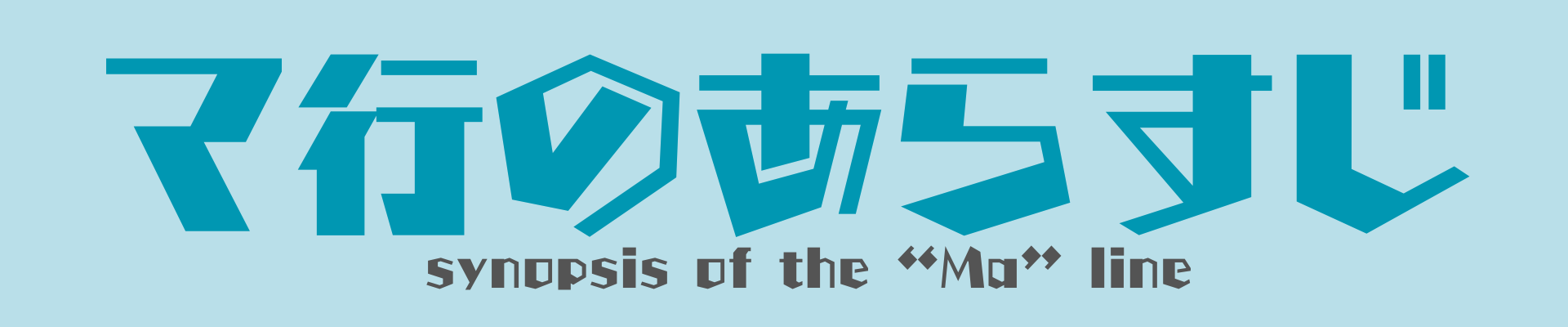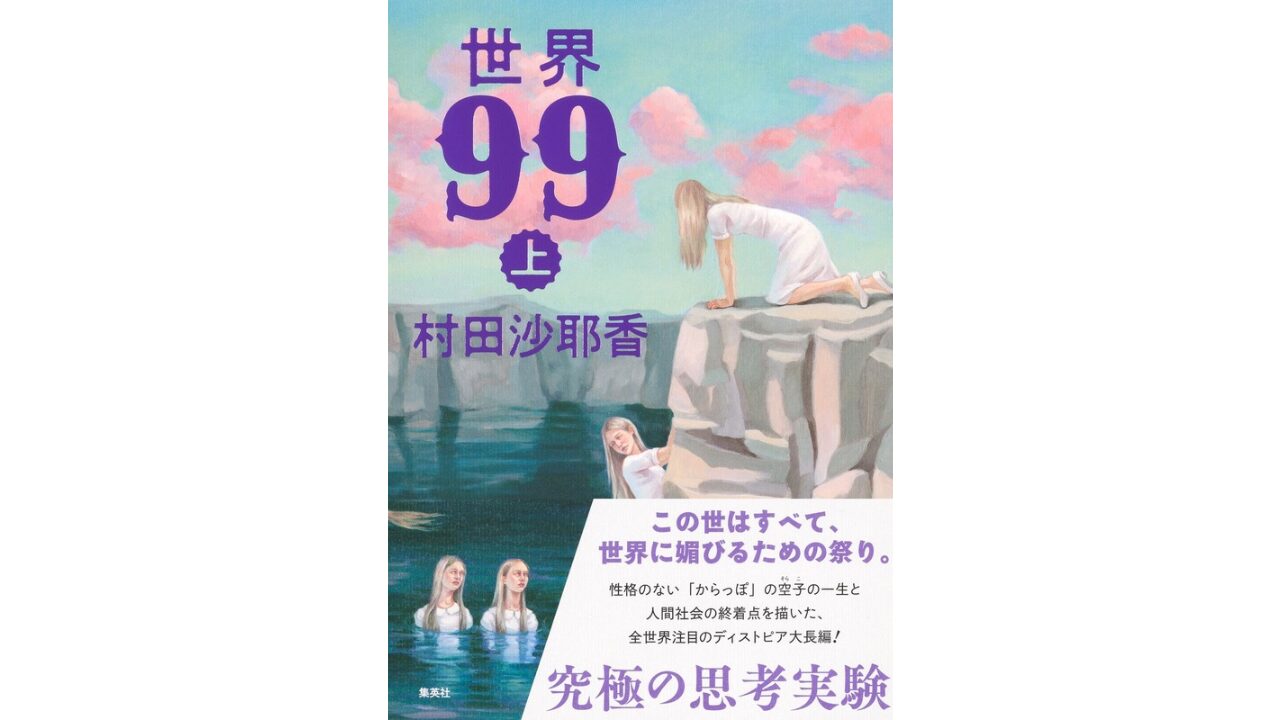世界99 上のあらすじ
性格とは自分ではなく他人が創るもの。では、初めに自分の性格を作り出したのは誰?
性格のない人間
如月空子には性格がない。相手の顔色や口調、雰囲気を呼応し、それに見合う自分になりきるトレースを繰り返して、コミュニティのごとに相応しい人格を作り上げていく。
家では可愛くて素直な一人娘の「そらちゃん」。幼稚園では他の子どもたちの手本になる「空子お姉ちゃん」。
いたいけな少女として私を見る白藤さんの前だけは「キサちゃん」で、学校では虐められないように浮かないように少しダサい「そらっち」でいる。
自分を安全に保ち、いかに楽に暮らしていけるかを考えると、キャラクターを使い分けるのが最善策だと思うのだ。
ピョコルンという救世主
父親は空子に何の不自由ない生活をさせるため、朝早くから夜遅くまで仕事をし、母親は家事をする道具としていいように使われている。
そんな空子の家にピョコルンがくる。動物園でも大人気のピョコルンをペットとして飼うにはお金も管理も大変で、皆に羨ましがられる。
時代の変化とともにピョコルンの存在意義が変わり、人々の暮らし方が一様に変化していく。
ディストピア超大作の上巻
性格のない空子のからっぽの人生と共に、人間が生きやすいようにと変わっていく日常。
どうか空想の世界のままであって欲しいと願う。誰も経験したことのないディストピア超大作、上巻。
世界99 上の名言
呼応がうまくいったとき、私はいつも、独特の空気の振動を感じる。相手が私を「自分と同類の人間」だと認識したとき特有の、親しげな安心感と、自分に近しい人間に出会えたという微かな感動が、波動になってこちらまで広がってくるのだ。
白藤さんに「呼応」することで、私はどんどんいたいけな少女になっていく。
こういうことには慣れていた。というより、私はいつもこういう感覚の中にいるのだった。私という人間を、私ではなく、周りの人間が作り上げていて、中にはなにもない。
それまでは、どちらも「わたし」だと思っていた。けれど、「空子お姉ちゃん」はみんなの創り上げたキャラクターであって、「わたし」ではないのだ、とわかったのだ。私は、このとき、自分には性格がないと知ったのだった。思えば「そらちゃん」だって、父や母の機嫌を窺っていたら出来上がった人格で、別に自分自身の意思でそうなっているわけではなかったのだった。「性格」とは自分ではなく他人が創るものなのだ、とこのとき理解した。
大人はよく、交渉をすることがある。幼稚園の先生や、誰かのママ同士が、会話の奥で探り合っているのを感じることはよくあった。父と母の場合、弱者である母のたった一つの持ち駒は、嫌味なくらい従ってみせることだった。父は、それが母の唯一の反抗であることに、まったく気がつくことかできないので、母の交渉はいつも失敗していた。
特にやりたいことがない人間は、やりたくないことを消去法で削除しながら自分の未来を決めるしかない。「夢」はきらきらした麻酔のようで、それがあるとたくさんの現実が麻痺するみたいだ。
そういう言葉は、インパクトがあるだけで土台がないのでふゆうしていて、相手の身体の中に入り込んで爆発する。そのためだけの言葉なのだ。根拠がないので、言葉を投げつけられた人間は理論ではそれを身体から追い出すことができない。だからどうすることもできず、身体の中で破裂した言葉を抱えたまま、ただぼろぼろになっていくしかない。そういう光景を、教室で何度も見てきた。
世界99 上の感想
とんでもない作品に出会ってしまった。想像の範疇を超え、自分の頭では到底処理できない事象の数々に、ただただ頁を捲ることしかできない。
性格のない人間。この時点で共感などできっこないはずなのに、全てを俯瞰して全ての人間の内情を言語化し、それに見合う返答をする空子が、あまりにも出来た人間だと感心してしまう。
それは、普段相手の心を分かりたいと思う自分の欲望の憧れなのだと途中から気付かされる。
そう、みんな誰だって所属するコミュニティによって性格も話し方も感情も変えているではないか、と。社会に適応するため、自分を殺す。相手に合わせる。そんなこと日常茶飯事ではないか。
空子自身は呼応とトレースを繰り返していくことしか生きていけない自分を早くも認め、特別な自分に酔いしれてさえいる。
しかし、キャラクターを作り続けていくうちに、孤独という感情に芽生える。ああ、どうか救われてくれと願わざるを得ないくらいに、空子の人生にはなりたくないと強い拒絶感が襲う。
結局は幸せになれない不条理を目の前に、女性としての尊厳さえ失う空子に、ピョコルンが救世主となることで、秩序が保たれていく。まさに弱肉少食。
こんなにも既成概念をぶっ壊された気持ちになる作品にも関わらず、あくまでも日常空間がベースにあり、人間誰しもが抱く嫉妬や妬み、苦しみ、性への衝動が淡々と描かれているだけという恐怖。
フェミニズムへの描写は、出ました村田節!分かりたくもないし見るに耐えないけれど、現実にもあることなのだよなと諦めが勝つ。
気持ち悪さへのベクトルは非常に共感する部分が多いので、リアルさに苦しみながらも、私だけの偏見でないと安心した。
一切の息抜きも余白も持てぬまま、上巻は目眩く展開に終わった。下巻はどうなるのか、期待しかない。